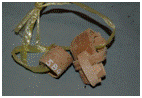佐治の板笠(国の登録有形民俗文化財)更新日:

佐治の板笠は、現鳥取市佐治町中・栃原で、少なくとも江戸初期から昭和30年頃まで、重要な産業として生産されていました。この板笠は、編み込みをされた丸みがある六角形をしており、一般的な菅笠のように竹などの骨組みを持たない木製であるため、大変丈夫でありながら、しなやかで軽いことが特徴で、県内の因幡地方はもとより、伯耆地方、辰巳峠を越えて県外は岡山方面にまで出荷されていました。
板笠は、町内の山に自生する「とうかえで・うりかえで」の木を材料にして編んで作ったものです。太い原木を小割りにして年輪を利用しながら、厚み0.2mm・幅5mm・長さ1mほどのテープ状に、剥いで作った「かさぎ」を編み組んで、「あごひも」をつけた骨格のない六角形の美しい「かぶりがさ」で最盛期には、年間1,000枚ぐらい作る家があって、その代金は1俵60kgの米を25俵も買うことが出来る計算になるなど、経済を大きく潤しました。丈夫なこと・軽くて被りやすいことが良くて、とても広い地域で愛用されました。
国の登録有形民俗文化財に登録されました
平成22年3月11日に『佐治の板笠製作用具及び製品』107点が文化財保護法第90条第1項の規定により文化財登録簿に登録されました。(内訳)製作用具94点製品類13点
『佐治の板笠製作用具と製品』107点は、板笠製作全工程の用具を網羅する貴重なものです。佐治歴史民俗資料館に保存されている用具と製品はすべて佐治町内の個人から寄贈されたもので、使用年代は昭和期のものが中心となっています。
内訳
- 原材料となる原木の採取とその運搬用具
- 原木を割り加工して編み込みの原材料となる笠木とする「小割り」用具、
- 小割りした木を笠木と呼ばれる薄板状に剥ぐ「へぎ」用具
- 笠自身を製作する「編み組み」用具
- 笠を頭に止める「紐つけ」用具
- 製品及び鑑札

佐治の板笠製作用具及び製品(一部)
佐治歴史民俗資料館保存
|
工程 |
道具 |
使用方法 |
||
|
原木準備 |
※1月から2月下旬に行う。凍った雪の上で採取する。カンジキは使用しない。 |
わらじ |

|
山で原木採取時に履く |
|
つまご |

|
山で原木採取時にわらじにかぶせ、足を保護する。 | ||
|
はんばき |

|
山で原木採取時に膝につけて膝を保護する。 | ||
| 鋸 |

|
笠木の原木であるウリノキ、トウカエデ、サクラを切る。長さを測る。 | ||
| 鉈 |

|
枝を払う。 | ||
| おいか |

|
原木を運ぶ。 | ||
| 背あて |
|
原木を運ぶとき、背中にあてて、背を保護する。 | ||
|
小割り |
鉈 |
|
原木を割る。 | |
| 割り包丁 |
|
原木を割る。使用しない板笠師もいる。 | ||
| 矢【くさび】 |
|
原木を割るために使う。 | ||
|
木槌 |
|
鉈、割り包丁を叩き、原木を割る。 | ||
| 指の保護具 |
|
割り包丁で原木をテープ状に裂くときに、指を保護する。 | ||
|
へぎ |
割り包丁 |
|
小さく割ったり、厚みを揃える。 | |
|
編み組み |
本体つくり |
笠編台 |
|
この上で編む。笠に丸みを持たせることができる。 |
| 寸木 |
|
編み込みの寸法を計る。大きさに応じて、6寸1分(中判用)、7寸2分5厘(大判用)の寸木を使い分ける。 | ||
| ものさし |
|
2尺。笠木の長さや笠の大きさを測る。 | ||
| 頭つくり | 笠包丁 |
|
桜皮の薄皮をはがし、美しくする。頭の端を切り揃える。 | |
| 裾のまとめ | 笠包丁 |
|
編み上がり、編み止めの後、笠木の端を切り揃える。片刃である。 | |
| 覆い(頭付け) |
通し木 【編み棒】 |

|
頭を本体につけるときに使用。 | |
| 紐つけ |
通し木 【編み棒】 |
|
紐をつける紐を挿し込むときに使用。 | |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0858-88-0218
FAX番号:0858-88-0219