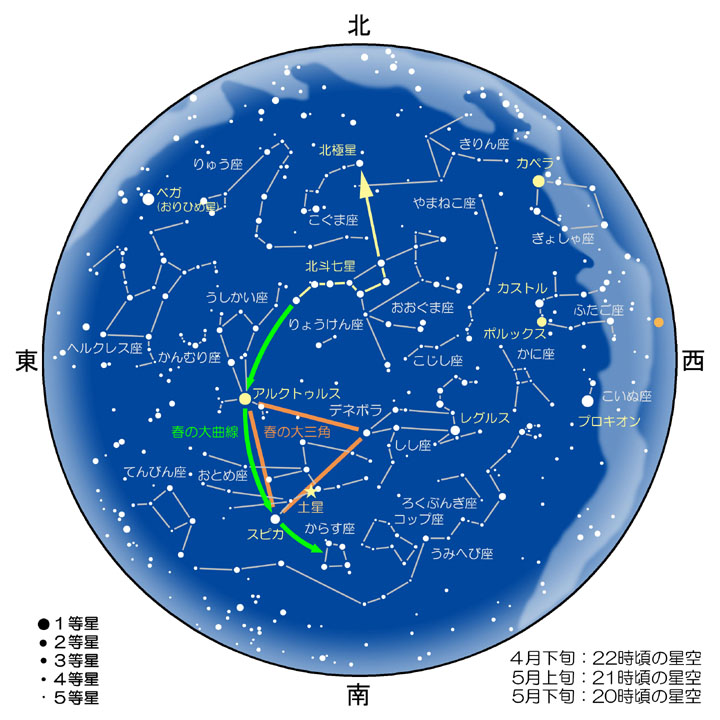|
「来る星の光は絶えずして、しかももとの光にあらず」。前回の最後の文章です。天文学で取り扱う星からの情報は、光などの電磁波ですね。電磁波の中には、光、電波、赤外線、紫外線、その他X線や宇宙線など粒子線も含まれます。これらの電磁波は、総ての物体から放射されていて、それぞれ放射源の温度に対応します。高温ほど波長が短く、低温になるほど波長が長くなります。皆さんを取り巻いている多くの物、言い換えると取り巻く環境からもその温度に見合った波長の電磁波が出ています。これは、例えば新型インフルエンザが発生したとき各地の空港で乗客の体温を検知するのに使われたサーモグラフィーでおなじみでしょう。
さて、私は講演や執筆に際して、「天文学は、考古学」だ、と言い続けています。何故でしょう。理科年表の2010年版によると、光の速度が観測から1秒間におよそ30万kmの速さであることが1676年・デンマークのレーマーによる木星の衛星の食の観測から知られました。それまで、光の速度は無限だ、と信じられていたのですが、この発見によって有限になり、しかも宇宙が有限の大きさになったのでした。科学者の間に大きな波紋を生み出したのはいうまでもありません。宇宙が、有限の大きさなら星までも有限の距離となります。有限の距離から、有限の速度で発せられて届いた光は、発せられた時の情報をもっていることになりますね。
方丈記に戻りましょう。「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」です。水を光に読み替えるとどうでしょう。星からの光は絶えることなく届きますが、決して同じ光ではありません。そして、留まることを知らないのです。光源を出発した光(電磁波)はその出発した時の情報を保持したまま我われに届いているのです。
星までの距離や遠くの銀河までの距離を表すのには光年という単位が使われます。これは、単に距離を表わしているだけではありません。そうです、時間を表わす単位でもあるのです。太陽までは光で8分ほどですが、これは8分ほど前に太陽を出発した光で、8分ほど前の太陽の情報を持っていることになるのです。同じように、遠くの銀河についても距離は時間で、そしてそれは決して現在の状況ではなく経過した時間だけ遡った時点の状況だというわけなのです。
考古学という学問の分野があります。身近な例として、昨年2010年は平安遷都1300年で、古都・奈良ではこの記念すべき年を祝う行事が繰り広げられました。また、各地には多くの遺跡が残り考古学者によって発掘が行なわれて、古代人の生活や、生活様式が解明されて来ました。キトラ古墳や高松塚古墳などは、天文図や東西南北の方角を守る四神(具体的には、玄武、白虎、朱雀、青龍)が描かれていたことによって有名になり、当時の人々の天に懸ける思いを知る手立てになりました。この考古学も、時間を遡ることによって過去を知ることができるという大きな意味を持っていて、これも一種の「親探し」だと私は考えるのです。
この発掘という行為と、流れ来て流れ去る光を手立てに過去の宇宙を見て考えるという行為を見比べるとき、とても良く似ていることに気付きませんか。
よく晴れた暗い夜、ふと見上げる空に何気なく光る星。その光を手立てに、光の速度を求めた人。また、その光を見つめることによって星の移動を知って距離を求める方法を編み出した人。古代にあっては、星の並びに興味を持って星座という区分けを行い、季節を知る手立てとした人。数多くの人々が、星に頼りを求め「河の流れのように」過去から現代まで連綿と受け継ぎ、そして未来へと引き継ぎの役割をそれぞれ請け負っていることを改めて知ることになるでしょう。私が「天文学は考古学だ」と言う所以なのです。
佐治天文台の晴れた夜。頭上には、大小無数の星の輝きを見ることができます。旅をするにしても、また何かを学ぼうとするときにも、引率者や参考書があるととても助かりますね。佐治天文台の、研究員はこのような時の支えになることを願って、日ごろの研鑚に務めているのです。研究員とお友達になって、星とのつながりを一層強くしてください。
|