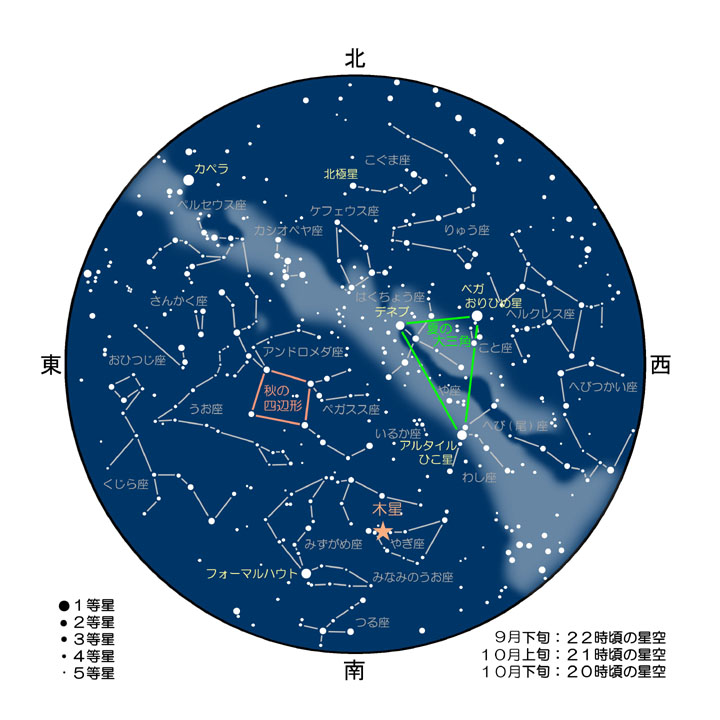|
日本の天文の歴史は、今までにも書きましたように中国から渡来した「観象授時」が、その目的でした。従って、中国からの新知識が渡来するまでは、日本独自の発達は見ることができませんでした。つまり、天文台と称して天象を観測してその示す意味を解き明かそうとするような試みは江戸幕府によって開かれた天文台(浅草天文台)が暦の作成に携わるまでは、全くといってよいほど記録に見ることができないのです。
ただし、その間でも吉備真備によって天平7年(735年)に中国から新しい暦や天体観測の道具がもたらされ、天文と暦が同列に考えられ始めると、暦の改定のための天体観測が行われようとし始めたのでした。しかし、これも当時は暦に関係のある事象や天の異変とでも言えるような現象に限られていて、多くは公家の間に流布していたもののようです。平安朝初期の陰陽家・賀茂保憲(やすのり)(?から977年)の時に歴道を実の子・光栄(みつよし)(939から1015年)に、また天文道を安倍清明(921から1005年)に伝えたという記録が残されていて、天文と暦が分離し、暦を賀茂家、天文は安倍家(土御門家)の家の学問になったのでした。天文と暦が分離してそれぞれの方向に進むなど、暦といえば誰でも天文を思い浮かべる現在では思いも及ばぬことではないでしょうか。
さて、長い空白時代を過ごして来た日本の天文観測の歴史ですが、世界の情勢にも大きな違いはありませんでした。即ち、ちょうど同じ頃のヨーロッパはいわゆる中世の暗黒時代といわれる頃に相当します。この暗黒時代の夜明けとも言われるのが文芸復興・ルネッサンスなのです。この頃に多くの俊才が現われ、コペルニクスやガリレオ、さらにケプラーなどが天地をひっくり返して地動説を公表し、ニュートンによって確定したのでした。日本も、この事実を鎖国中にもかかわらず手に入れ新しい天文学の機運が芽生えてくるのでした。渋川春海は元禄2(1689)年に江戸本所二つ目の自宅内に天文台を築いたが、元禄16(1703)年に江戸駿河台の新屋敷にこの天文台を移築したというそうです。もっとも、この天文台も暦の編纂に役立てようというもので、天体観測が目的ではなかったのでした。
関連する小惑星(5466):Makibi(吉備真備)、(5541):Seimei(安陪清明)、(9254):Shunkai(渋川春海)。
|