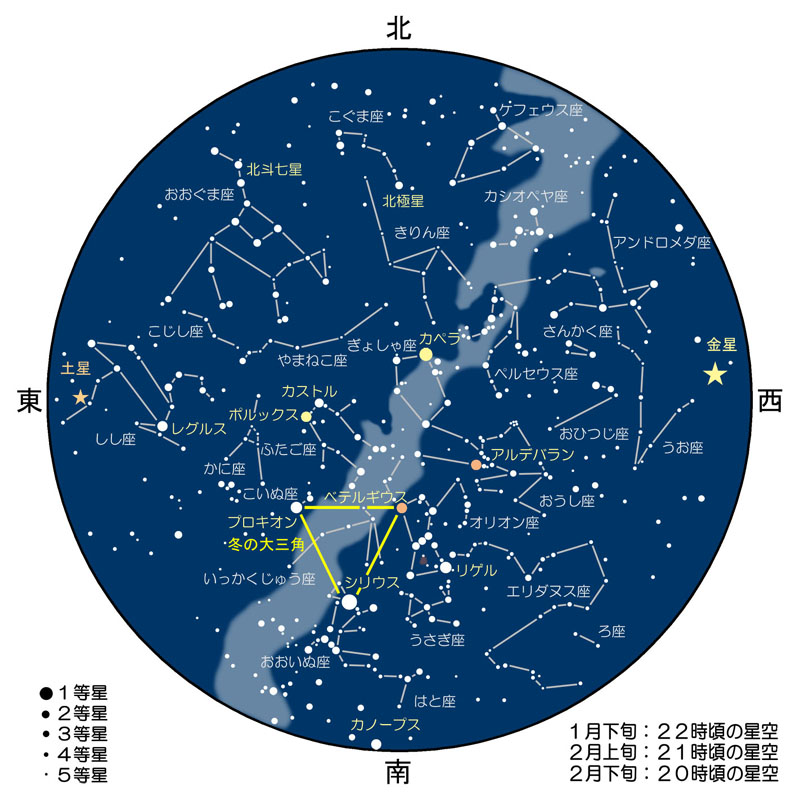天文セミナー 第140回
『望遠鏡物語(3)』『望遠鏡物語(4)』
|
長大な、いわゆる空気望遠鏡は、取り扱いがとても難しく、困難を極めます。この困難を克服するための研究が始められたのでした。1666年になると、有名なアイザック・ニュートンが、白色光が透明な物質に入って屈折するときには必ず波長ごとの色に分かれることを発見したのです。ところで、光が反射するときには物質の中を通過しません。このことは、光は色ごとに分散しないと言うことなのです。1663年には、反射鏡を使った望遠鏡のアイデアがグレゴリーによって発表されていましたが実際にこの反射望遠鏡を製作したのは1672年で、作者はニュートンでした。これがいわゆるニュートン式反射望遠鏡です。 |
望遠鏡物語(4)
|
世界でもっとも大きな口径を持つ屈折天体望遠鏡はアメリカのヤーキス天文台の口径101cm、口径比19で1897年にクラークによって製作されました。その他、アメリカのリック天文台の90cm、口径比19のものが1888年の製作、そしてフランスのムードン天文台の口径83cm、口径比20と続きます。日本での最大口径のものは、国立天文台の口径65cmと京都大学飛騨天文台の同じく65cm屈折望遠鏡です。屈折望遠鏡の最大の悩みは、なんと言ってもレンズで集まった光がガラス材の中を通過して屈折し焦点を結ぶことにあります。更に、そのレンズを保持するためには強固なレンズ枠を必要とします。そして、枠に取り付けたままでレンズの向きが上下左右に変化させられるために起きる、レンズの変形に対する考慮もしなくてはなりません。 |
| 次回も、お楽しみに |