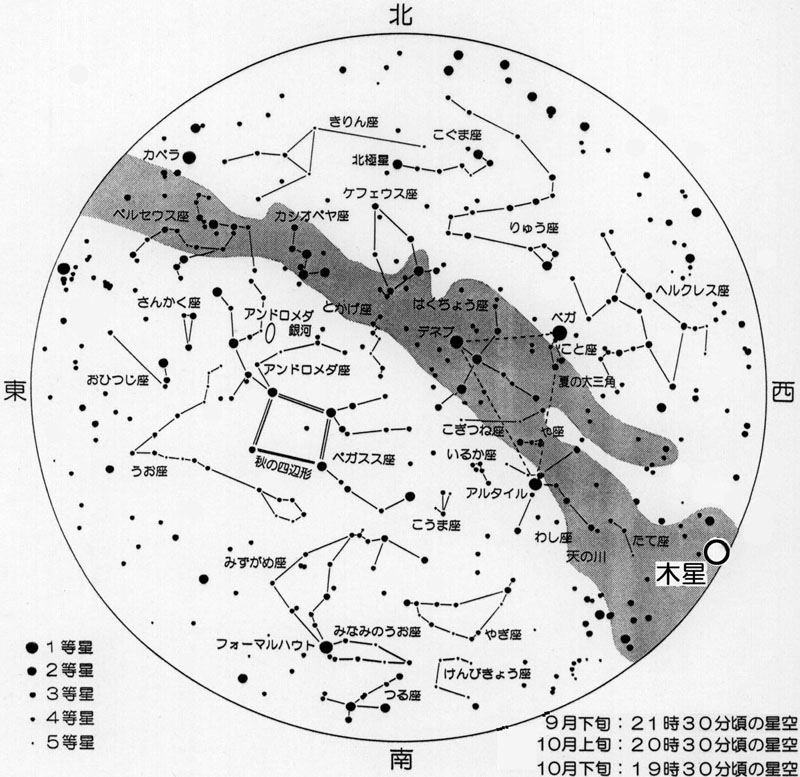|
大分以前のことになりますが、「子午線の祭り」という題名の小説が評判になったことがありました。天文に関係する、しかも天文座標系に直接関わる題名だったので今でも頭の片隅に残っています。
この題名が示すのが、北極から天頂を通り真南に到る仮想の直線、つまり子午線です。この子午線と地平線との組み合わせで作られた座標系が天文学や測地学、更に航海術に大きく寄与してきたのでした。真北を表わす言葉として正子、真南は正午。方位を干支で表わした時の表示で、この名残が時刻の正午、つまり太陽が真南に有る時を表わす言葉です。
さて、日本で現在使われている時刻制度は、イギリスの旧グリニッジ天文台のエアリーの子午儀の中心を通る子午線からの経度差に基づいて決められています。そして、日本中央標準時の原点は東経135度です。これは時間の差にして、ちょうど9時間。パソコンや、携帯電話で使用しているメールに表示されている+9.00という数字がこの値に相当するのです。ところで、この子午線は地球の表面に使われるだけではありません。天体の位置を測ったり、示す場合にも使われてきました。今から10年ほど前までは、大きな天文台には必ず子午線に沿ってだけしか動かない望遠鏡がありました。子午儀、又は子午環と呼ばれる機械で、望遠鏡の片側、又は両側に目盛りが刻まれた大きな環を持っていました。この目盛りは非常に精度が高く、更に副尺(バーニア)によって細かく目盛りを分割し読み取ることが可能でした。この望遠鏡の役割は、天体の位置を高精度で観測して求めることでした。子午線に沿って、水準器で決められた水平方向からの高度を、時刻と共に観測します。こうして得られた星の位置を元に他の星たちの位置を求め、さらにその位置を使って時刻を決定していたのです。そして、更に恒星の位置だけでなく惑星の位置観測から惑星の運動理論の改良、もう一歩進んでQSO(クエーサー)などの位置観測から銀河系の骨組みを知り、銀河系の見かけのねじれなどから回転方向や速度の分布まで求めてきたのでした。水準器と子午線を使用して星の位置を求めること、つまり目盛り環以外には頼ることの無い基本的な天文観測でした。こうして築かれたのが、位置天文学で、天文学の基本でした。

|