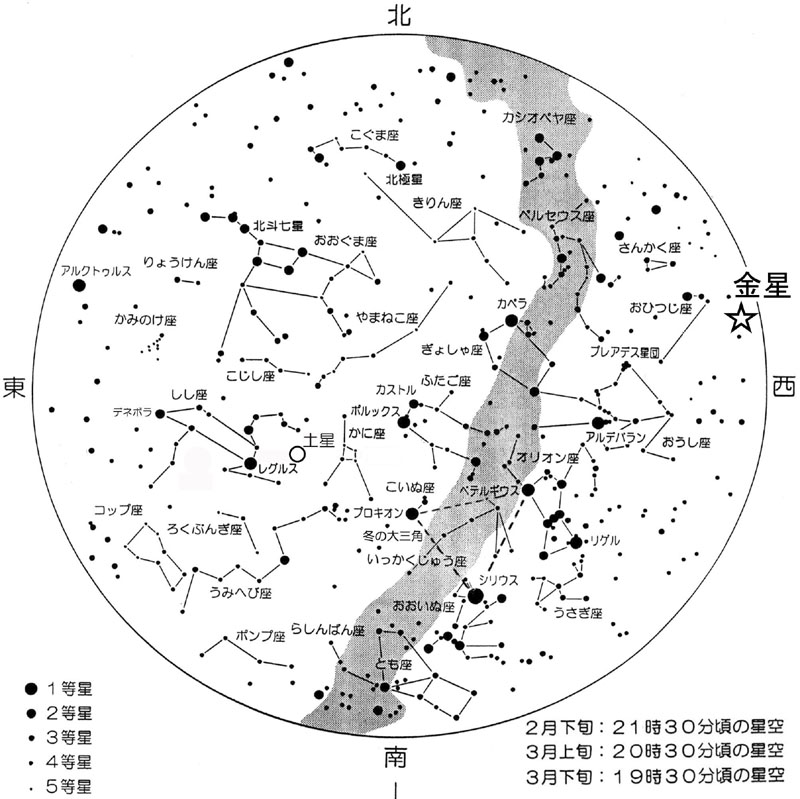天文セミナー 第117回
『超新星1987A』『地球に接近した小天体』
|
1987年2月24日、新天体の発見を知らせる1通の国際電報が東京天文台に届きました。南半球の夜空に輝く大マゼラン星雲に、超新星が出現したという内容です。あいにくマゼラン星雲は日本など北半球の国では見ることはできません。通常では、”そうなのか”と今後の成り行きを傍観するだけになるのですが、そのときは違いました。ちょうどその頃、東京大学理学部が岐阜県高山市の鉱山の地下深くに建設していたニュートリノの観測施設、カミオカンデがほぼ完成していたのです。国際天文電報の中継とでもいえるような仕事をしていた私は、早速この発見電報を東京大学理学部の物理学教室に伝えました。応対に出られた方の話では、カミオカンデは目下試験運転中で、データが残されているかどうか不安だが、それでも記録を確かめましょうとのこと。数時間の後、連絡があり少数だが何かの痕跡が記録されていると。多くの検証の結果、この記録が大マゼラン星雲で発生した超新星爆発によるものであることが確信され、世界最初のニュートリノ検出に関わる出来事として小柴氏のノーベル賞の受賞へと進む最初の一歩でした。このニュートリノの検出と、光や赤外線、さらに電波などの観測から、超新星爆発のメカニズムが次々に研究され、恒星の生涯についてのシナリオが一層詳しく判明して大きな成果を挙げることになったのでした。超新星の爆発に伴う超高温、超高圧の環境の元で、多くの重い元素が作られ、その重い元素が爆発によって宇宙空間に放出された後、再び重力で集合して新しい次世代の恒星が作られて行くこと。その1つが我々の太陽であることも改めて確認されたのでした。こうして宇宙は成長し、輪廻転生を繰り返しているのです。この繰り返しが、宇宙の年齢137億年の歳月を経て今日に至っていることになるのです。 |
地球に接近した小天体
|
先月は、世間を騒がせた特異小惑星・トータチスのお話でした。この天体以外にも、それまでも幾つかの地球に接近してきた小惑星が知られています。最も古くは、1898年8月13日にベルリン天文台で発見された433番エロスがあります。この星は、その後の観測から地球に接近するような軌道をもっていることが知られ、ちょうどその頃から話題になっていた地球と太陽の間の距離、つまり1天文単位の長さの決定に応用されたのです。それは、エロスの軌道を精密に決めることによって太陽からの距離が求まり、さらにその値を解析することによって地球から太陽までの詳しい距離が求められるという天体力学から導かれた方法なのです。実際の観測が行われたのは1930年代の頃ですが、1929年に設置されたばかりの東京天文台の口径65cmの屈折望遠鏡もこの観測に一役担うことになったのです。星の精密位置観測には、焦点面でのスケールが問題になります。スケールが大きいほど測定誤差が小さくなるからなのです。65cm屈折望遠鏡の焦点距離はとても長く1023cm、つまり10m23cmもあって、1mmが角度でほぼ3分に相当します。この望遠鏡を使って、当時の研究者は苦心の末、太陽と地球の間の正確な距離を求めようと試みたのでした。 |
| 次回も、お楽しみに |