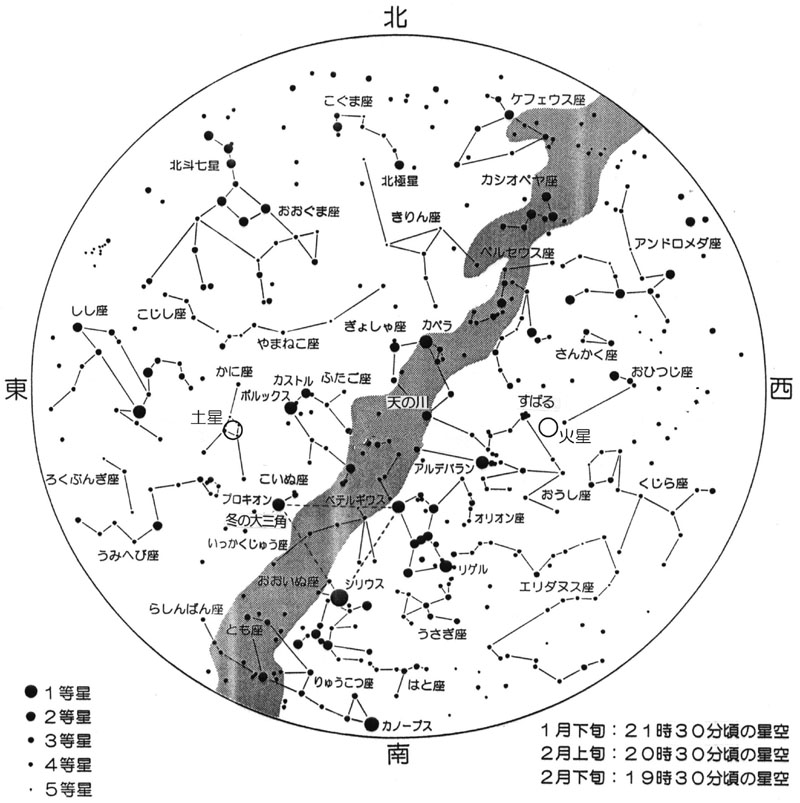天文セミナー 第104回
『イトカワとはやぶさ』『美術館の絵』
|
2003年5月9日に、当時の文部省宇宙科学研究所(現在の宇宙航空開発機構宇宙科学研究本部)の鹿児島県内之浦にある実験場から小惑星糸川(25413)Itokawaに向けて打ち上げられたのが「はやぶさ=MUSES-C(ミューゼス(C)」でした。この「はやぶさ」が、小惑星Itokawaに接近し、表面の物質を採取して地球に持ち帰る、というサンプルリターン計画です。計画が成功すると、太陽系の生まれたときの状態や、その後の進化の様子を知る上で大きな成果が期待されています。さて、昨年この「はやぶさ」がItokawaに接近して撮影して地上に送ってきた写真によると、大きさは600mX300mほどで、ジャガイモのような形に例えられています。そして、表面には大小のクレーター、穴ぼこが見られましたが、今までにも小惑星にはこのようなクレーターがあることは知られていました。このクレーターが作られたのは、小さな物質、言い換えると小惑星よりもっと小さい無数の天体が太陽系の中を運動していて、それらが小惑星に衝突した証拠であろうと考えられています。また、最近になって月の表面の数々のクレーターが、やはり同じように小さな天体が衝突してできたと国立天文台の研究者が報告しています。 |
美術館の絵
|
昨年の初秋、ある美術館で開かれていた「ミレー、コロー、バルビゾンの巨星たち」というタイトルの絵画展を見てきました。そこに展示されていた絵画のいずれもが近代日本のいわゆる西洋画のルーツになっていて、この時代に続くのがいわゆる印象派の絵画です。19世紀から20世紀に制作された絵画で、中には私にもなじみ深い作家の絵があり、実物に触れる喜びに包まれました。会場を進むうちに、ふと目に付いたのが、いずれも農作業を終えて家路につこうとする前の一時を描いた2枚の絵。黄昏の西空には日没後の残光が茜色を見せ、三日月がそろそろ光を増そうとする情景です。ところがこの三日月の欠けた方向がちょうど正反対でした。しかもこの2枚の絵が並べて展示されていたので、強い印象を受けました。なぜ、2人の作者は三日月の欠けた方向を反対向きに書いたのでしょう。北半球のフランスはパリの近郊で描かれているにもかかわらず、です。考えた結果は、1人は自然の現象に忠実に描くこと、つまりしっかりと残したスケッチをによって自分の思いを表現し、もう1人は見た情況を頭に刻み込んで帰宅後にアトリエで制作したのではないかということでした。2作品とも、すばらしい作品で、何時までも脳裏に深く残るような印象深いものだっただけに不思議な思いで帰宅したのです。帰宅後、計算で調べたところ、正しい方向が欠けた月が描かれた作品は1889年の9月か10月の月末のパリの郊外での夕刻であろうと推測したのです。同じような思いをしたことが過去にも数回以上あり、天文学的な手法で解析すると、意外にも制作の場所や年月日までも推測することが可能です。また、記録に残るような天文現象があった時など、絵の作家、つまり画家がその現象を絵の一部分に書き残すようなことがあるようです。残された絵の中に、一寸でもそのような箇所を見つけることによって、描かれた絵の場所や年月日、さらに背景や作者の心情までも推測できるのです。天文学の別な面での喜びかも知れませんね。 |
| 次回も、お楽しみに |