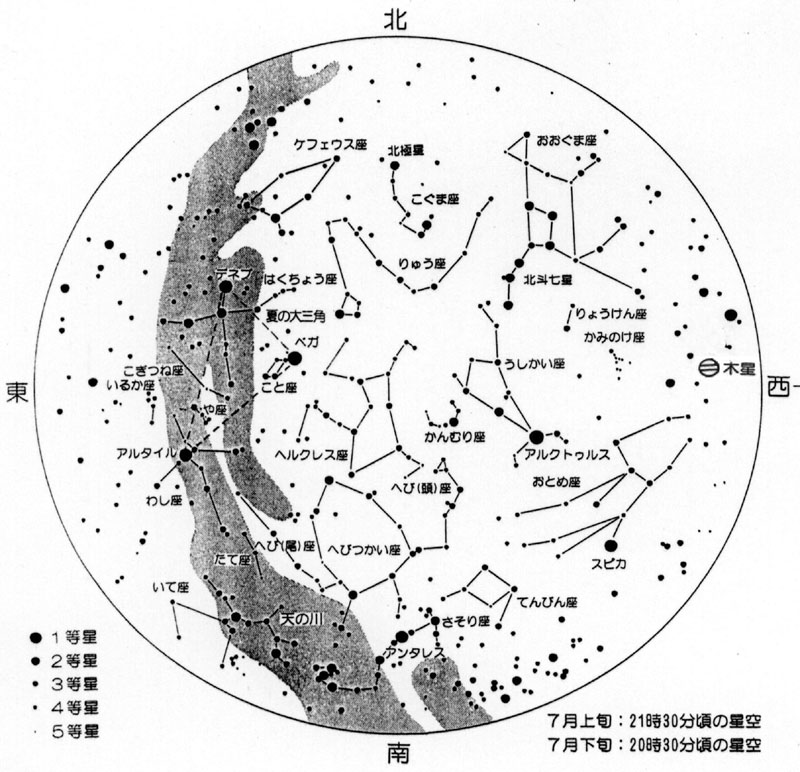天文セミナー 第85回
『伊能忠敬』『時刻と時間』
|
この天文セミナーを始めて、速いもので7年を経過してしまいました。私の勝手なお喋りを長い間ご愛読頂いたことを感謝いたします。
当時の天文測量は、大きな分度器のような四分儀を使って北極星など星の地平高度を測り、横型の四分儀を使って目的物の方位を測るのです。しかし、最も苦労したのは経度の決定でした。経度の差は天体の南中時刻の差として求められるのですが、正確な時刻を保持できるような時計が必要です。そこで使われたのが、一種の振り子時計でした。 |
||
時刻と時間
|
いつも何気なく使っているのが時間という言葉。電車や列車が発車する時間は?などと使いますね。ところで時間ってなんでしょう。考えてみたことがありますか?。一度、考えてみることにしましょう。先ず、時間とは「ある瞬間から経過した時刻の積み重ね」で、時刻とは「瞬間」のことと覚えましょう。したがって、電車や列車が発車するのは「時刻」で、発車してからの経過が「時間」で表されることになります。
1950年代のことです。NHKのテレビ番組に「私の秘密」という人気番組がありました。ある日突然、この番組に当時の東京天文台の研究者が登場したのです。そして、私は地球の自転速度が遅くなっているのを見つけました、と秘密を告白したのです。当時の時計は現在の精度には遠く及びませんでしたが、東京天文台は日本の「時」の管理者として最も高精度の時計を設置していました。当時の高精度の時計は、現在私たちが日常使っている水晶時計で、原子時計などは研究され始めたばかりの頃です。この水晶時計が刻む「時」が地球の自転速度が遅くなって行くことを教えてくれたのでした。 |
||
| 次回も、お楽しみに |