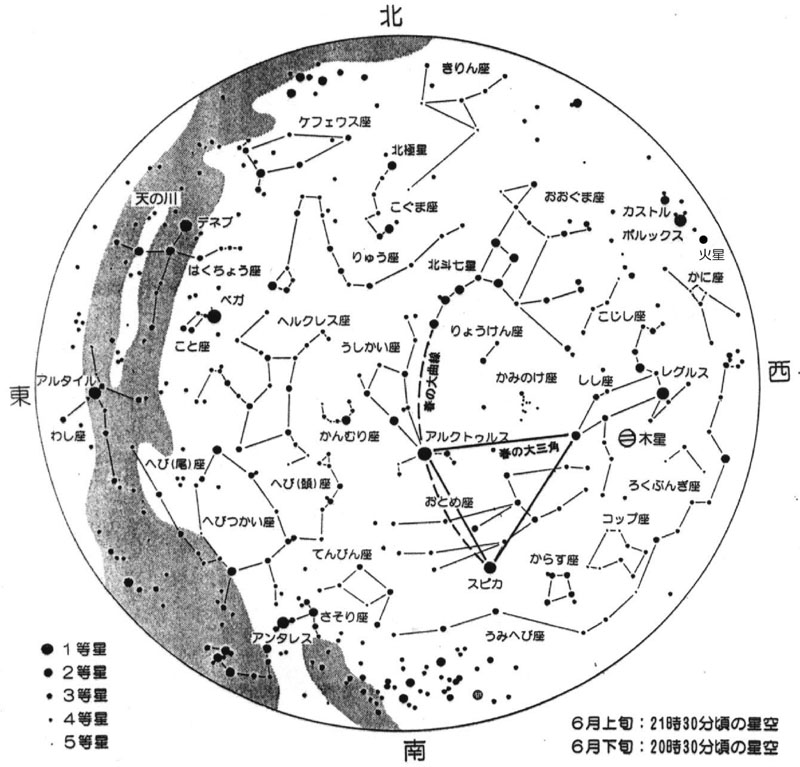天文セミナー 第84回
『金星の太陽面通過』『振り子の等時性』
|
1874年(明治7年)12月9日。世界の科学先進国から、金星の太陽面通過を観測観測しようと多数の天文学者が日本を訪れました。当時の天文学は、いわゆる位置天文学が主流で、現在のような天体物理学はまだまだ未発達の状態でした。何しろ、1874年と言えば東京大学(1877年=明治10年創立)の本郷構内に理学部付属観象台として東京天文台が産声を上げたのが1878年=明治11年のこと。わが国は、西欧諸国に追いつけとばかりに、新知識を貪欲に求めていた頃のことでした。
ところで、1874年に世界各地から日本を訪れた観測隊は、横浜、神戸、長崎などに観測地を決め観測に当たりました。しかし、観測地の経緯度や、正確な時刻を決めるために多くの努力を必要としたのです。経緯度は、天文測量術を使いますが時刻が分からなくては精度は上がりません。当時敷設されたばかりの海底電信網を利用して、ヨウロッパの天文台が発信する時報を受信して時刻を決め、経緯度が決定されたのです。金星の太陽面通過がもたらしたのは、まさに「科学黒船の来航」だったのでした。この時の金星の太陽面通過観測記念碑が先述の3都市に建立されていて往時を忍ばせてくれます。 |
||
振り子の等時性
|
6月10日は時の記念日ですね。日本書紀には斉明天皇6年夏五月に皇太子(後の天智天皇)初めて漏刻造ると、また天智天皇10年夏卯月に漏刻を新しき台に置くと書かれています。そして、この記録を元に、決められたのが時の記念日です。
こうして発見された振り子の等時性が、その後振り子時計として多くの人に時を知らせたのでした。しかし、この振り子時計は動力として錘が使われていたのでその錘を何らかの方法で巻き上げなくてはならず、また持ち運びがとても大変でした。この不便を解消しようとして考えられたのがゼンマイ仕掛けの方法でした。ゼンマイが巻かれた状態から解けてゆくときの力を利用して、時計の機械を動かそうと言うのです。このゼンマイ式の時計が発明されたことは「時を計る」上での大きなエポックになったのです。航海に必要な時刻の保持に使われるのがクロノメーターと呼ばれる精密時計で、この名前はギリシャ神話に見られる「時の神クロノス」に由来しますが、このクロノメーターが金星の太陽面通過などの現象の観測に大きな貢献をしたのでした。 |
||
| 次回も、お楽しみに |